まずはじめに、わたしは宅建試験の勉強スケジュールで大失敗しました。
勉強期間の途中で「ヤバい、このやり方じゃ間に合わない!」と気づき、急いで軌道修正。猛烈な焦りの中でなんとか合格を掴み取りました。
だからこそ、この記事ではわたしの失敗(テキストメインの学習)を踏まえた具体的なスケジュールと勉強法を提案します。この通りに進めれば、皆さんはわたしの遠回りした期間をショートカットし、より短期での合格を目指せるはずです。
📅 失敗の始まり:1月〜2月は「読書」で終わる
宅建試験の本試験は毎年10月の第3週目。わたしが受験を決意したのは、本試験を約10ヶ月後に控えた12月でした。大体この時期には、翌年版の市販テキストも発売され始めます。
「まだ時間はあるし、まずは敵を知ろう」という気持ちでテキストを購入。そして年明けの1月、わたしは最初の1ページ目から読書のように読み始めました。
夜寝る前に数ページずつ。と、のんびりしたペース。2月いっぱいかけてテキストを読み進めましたが、この頃には「あれ?意外と範囲が広いぞ?」と、漠然とした不安を感じ始めていました。
💣 3月に直面!「絵本」と「長文小説」ほどのギャップ
3月に入り、一通りテキストを読み終えたので、次は問題集へ。
1ページ目から解き始めて、皆さんもきっとびっくりしたのではないでしょうか?
「え、テキストと全然違う問題じゃないか」「文章の難しさが段違いだ」と、わたしも驚愕しました。
例えるなら、
- テキスト:低年齢の子供用の、大きなイラストと少しのひらがなが添えられた「絵本」
- 問題集:大人用の、東野圭吾の単行本並に分厚い、小さな文字だらけの「小説」※東野圭吾作品は初めはその分厚さに驚きますが読み進めていけば行くほど面白く熱中しますよね。笑
…というと大袈裟かもしれませんが、あの可愛いイラストが文字だけにすると「こんなにいかつくなるのか!」という衝撃は、皆さんも共感してくださるはずです。笑
そこから、わたしは問題集を解いていこう!と進めましたが、最初のうちは1問ずつテキストと並べ、深く理解しようと進めていきました。宅建業法を終え、法令上の制限に取り掛かった4月。この頃から「このままではマズい」と感じ、平日2時間休日5時間を目標にの勉強時間を確保するようになりました。
💡 5月に気づいた決定的な失敗と学習法の転換
5月に民法に入ったところで、ある事実に気づきました。
「あれ?気づけばもう1月から始めて4ヶ月。試験まであと5ヶ月なのに、全然問題すら理解できていない……」
さらに致命的だったのは、民法まで進めて宅建業法に戻ったとき、前にやったことを全く覚えていなかったことです。
- インプット(テキスト読書)に時間をかけすぎたこと
- アウトプット(問題演習)が圧倒的に不足していたこと
- 時間をかけても、記憶が定着しない非効率な学習だったこと
この失敗を受けて、わたしは勉強法を180度転換しました。
- 問題集をメイン教材とする
- テキストは問題集の解説で理解できない部分の「補助教材」として使う
ついテキストをメインにしてしまいがちですが、合格への近道は問題集の周回にあります。問題集の問題をまず読み、答えを予測する(最初は全くわからないので、すぐに答えと解説を読んでください)。解説を見ても理解できない部分のみ、もう一度テキストに戻るという方法です。なるべく問題集の解説で完結できるようになると効率的です。
この学習法をしていくと、わたしはテキストは新品並に綺麗、問題集はボロボロという状況になっていきました。
次回は、実際に使用したテキストと問題の回し方について詳しくお話しします。

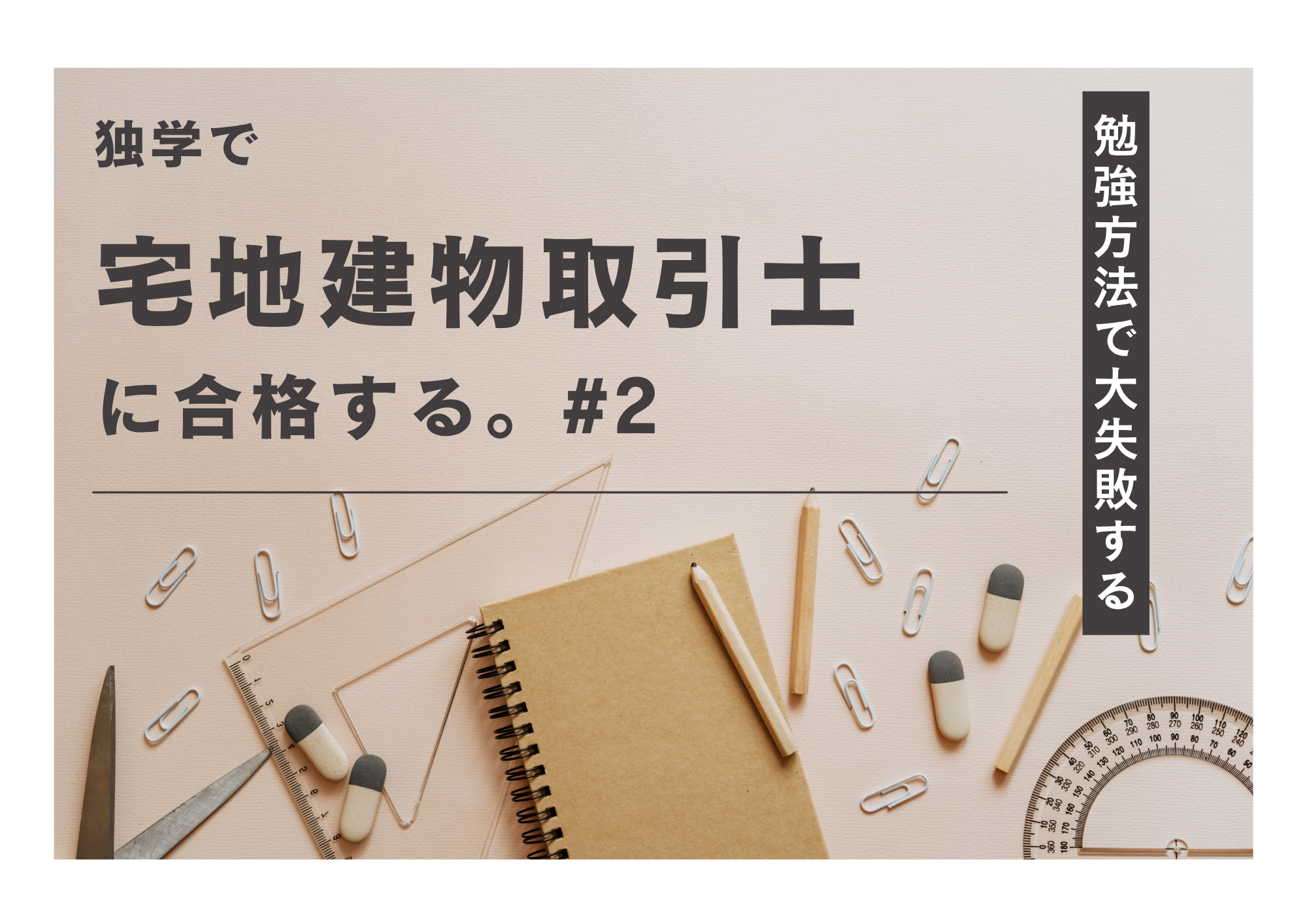
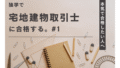
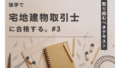
コメント